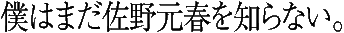

現在、僕の家にある184篇の詩はどれもシーモア自身によく似ている。最も控えめに言っても、音響効果 ですらシーモア同様に独特のものだ。
アルバム・タイトルの『Grass』からJ.D.サリンジャーの小説を連想する人が筆者以外にいるのかどうか、常識的なのか非常識なのか、多数派なのか少数派なのか、謙虚なのか傲慢なのか、平凡なのか非凡なのか、利口なのか馬鹿なのか、それはよくわからない。
ただ、『Grass』というタイトルから僕はシーモアやバディやフラニーらグラス家の人びとが登場する作品群(通 称“グラス・サーガ”)を連想した。もちろんサリンジャーの場合のグラスは“Glass”であり、このアルバムのタイトルとはスペリングが異なることは言うまでもない。けれども大多数の日本人が「グラス」という単語をカタカナ感覚で口にするとき、“R”と“L”の発音の差異に気を遣う者は少ないだろう。と書いた瞬間に気づいたが、佐野元春なら正確に発音するだろうな、きっと。
だけど僕は佐野元春じゃない。幸か不幸か。決して佐野元春ではない筆者はここで彼がこの20年の間に制作してきた膨大な作品群に思いを馳せる。「アンジェリーナ」から「イノセント」まで。サリンジャーの“グラス・サーガ”に倣って“モト・サーガ”とでも名づけられそうなそれらの作品群は無数のプロットやエピソードやモチーフが幾重にも織り込まれた壮大な物語のタペストリーだ。
言ってみれば佐野元春の作品は皆、どこかで彼自身の他の作品と繋がっている。たとえば「ハートビート」に登場する“小さなカサノバ”と“街のナイチンゲール”のその後の物語、というコンセプトで新たな作品集を選曲/構成しようと思えば、あるいは「ロックンロール・ナイト」で描かれた“川”と“橋”をテーマにした新たな作品集を選曲/構成しようと思えば、佐野はそれぞれに個性的なコンセプト・アルバムを作り上げることができるだろう。
コンセプト・アルバム? そう。それらの作品集にはコンピレーションとかオムニバスとかいう一般 的な呼称は似合わない。もしも佐野自身がそれを手掛けたとしたら、間違いなくコンセプト・アルバムと呼ぶにふさわしい作品集に仕上がっているはずだ。
作者自身によって『Grass』と名づけられたこの作品集も、敢えて言うまでもなくユニークなコンセプト・アルバムのひとつだ。そもそも佐野元春が過去の作品を寄せ集めただけの凡庸なコンピレーション・アルバムを作るわけはないのだが、それにしても、この作品集の構造や性格は予想以上に複雑なものだった。
古田たかしのタイトなドラミングに先導されたハートランド時代の未発表曲「ディズニー・ピープル」で幕を開けるアルバム『Grass』。佐野はこの作品集をひたすら陽気なパーティー・アルバムに仕上げることもできただろう。けれども彼は敢えてそうしなかった。
『Grass』は聴き手をトリップへと誘う。僕らは言葉と音楽によってトリップし、その世界でさまざまな経験をくぐり抜け、どこか別 の時空へと連れ去られる。それが飛び切り最高のトリップになるのか、それとも低空飛行に終わってしまうのか、それは聴き手の資質や気分や体調によって左右されるかもしれないが、いずれにしてもそれが痛いほど刺激的な体験だってことだけは間違いない。そして、聴き終えた後に残る感覚は僕らの人生そのもののように複雑だ。たとえばサリンジャーの“グラス・サーガ”の読後感のように。
ニュー・ハンプシャー州コーニッシュの山上で隠遁生活を送りながら発表するつもりのない小説をずっと書き続けているサリンジャーの“グラス・サーガ”の全貌を僕らがまだ知り得ないように、僕らはまだ“モト・サーガ”の全貌を知らない。それはこのアルバムを聴き終えたときに僕が得た貴重な教訓のひとつだ。たとえ過去の全作品を聴き得たとしても、そこには大きな謎が幾つも転がっている。頭の中ではクエスチョン・マークが螺旋を描いている。
僕らはもっと謙虚になるべきだと思う。
僕はまだ佐野元春を知らない。
もう一度、そこから始めてみよう。
|



