|
|
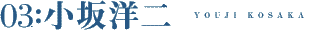
| 小坂洋二●1948年、神戸に生まれる。渡辺プロダクションを経て、1978年、EPIC SONY(現EPIC Records)に入社。最初に手掛けたアーティストは佐野元春。その後、TM NETWORK、大江千里、渡辺美里、岡村靖幸らを手掛ける。現在は「(株)パームビーチ」代表取締役社長。 |
|
|
ひと言でいえば“無尽蔵の才能”だと僕は思っていました。
::::::::ー最初の出会いを覚えていますか?
小坂 もちろん。よく覚えてますよ。「ドゥ・ホワット・ユー・ライク」と「彼女」が入ったデモ・テープを聴いて、すぐ彼に電話したんですよ。デモテープでの歌声や電話の声から“大きな人”を想像していたので、実際に会ってみたら意外な印象がありました。思っていたよりも小柄だったし、髪が長いわけでもないし、その頃のロックのイメージからは程遠い風貌の人だったので、印象的でした。
::::::::小坂さんにとっては初めて手掛けるアーティストになるわけですね。
小坂 そうです。僕は1978年の秋にエピックに入社したわけですけど、まだエピックそのものもできたばかりで、アーティストも少なかったですね。最初の1年間は“勉強”という名目で遊んでいたようなものでしたが、なにしろ制作担当だから、新人アーティストを見つけなきゃいけないだろう、ということで、いろいろなデモ・テープを聴いていました。200曲くらいは聴いたかな。その中に佐野君のデモ・テープがあったんです。
::::::::当時、すでにかなりの数のオリジナル曲があったそうですが。
小坂 彼はトランク一個分のデモ・テープを持っていました。佐野君はそれを“Music Bank”と呼んでいました。その“Music Bank”の中には本当にいろいろなタイプの曲があって、彼は作ろうと思えばどんな曲でも作れるんだな、と感じました。やろうと思えば何でもできる。ひと言でいえば“無尽蔵の才能”だと僕は思っていました。
::::::::最初のレコーディングを覚えていますか?
小坂 ええ。フリーダム・スタジオで「アンジェリーナ」や「バッド・ガール」などの4曲をレコーディングしました。大村雅朗さんのアレンジで、当時としては一流のスタジオ・ミュージシャンに集まってもらったんだけど、大村さんのアレンジにしても、彼らのプレイにしても、佐野君にとっては抵抗があって、どうしてもアレンジャーやプレイヤーへの注文が多くなるから、進行が滞るわけです。そうするとミュージシャンたちは僕に苦情を言いに来るし、アレンジャーの大村さんも困る。で、最後には「それなら自分でやればいいじゃん。冗談じゃない。俺たち、もう帰るよ」ということになる。だけど、ミュージシャンたちは皆、「しかし、あいつ、いったい何者なの?」と呟きながら帰っていきました。佐野君は彼らにそれだけ強烈な印象を与えたんですね。
::::::::当時から自分でプロデュースしようとしていたわけですね。
小坂 そうなんです。佐野君も当時はまだスタジオのこともわからないし、レコーディングのやり方もわからないから、プロデューサーやアレンジャーが必要ではあったのだけど、当時から自分でやろうとはしていましたね。だから彼はいろいろなことを物凄い勢いで吸収してましたよ。それが『SOMEDAY』で開花するわけです。
::::::::最初のセッションでレコーディングされた曲は……。
小坂 その最初のセッションでは「アイム・イン・ブルー」もレコーディングしています。結局、そのときにはアウトテイクになったんですが、その後、まったく新しく生まれ変わって、アルバム『SOMEDAY』に収録されることになるんです。
::::::::「アンジェリーナ」から「サムデイ」までのシングルを振り返ってみると、どの曲もビッグ・ヒットにならなかったのが不思議に思えますね。
小坂 僕も含めてスタッフ全員が「アンジェリーナ」は間違いなくヒットすると思っていました。僕らは「ナイトライフ」もヒットすると思っていたし、特に「ガラスのジェネレーション」はヒットしないはずがないと考えていました。だけど、ヒットさせることができなかった。「サムデイ」のときにはレコーディング中に「佐野君、チャートで何位になるか、小坂さんに約束させておいたほうがいいよ」なんて吉野金次さんにも言われたけど、これも残念ながらヒットとは言えない結果でした。これについてはレコード会社の宣伝力が弱かったからだと言われるかもしれません。なにしろ当時のエピックは素人の集団が熱意だけでやっていたようなものだったから、それもたしかにあったのかもしれない。でも、音楽業界の人たちも含めて、佐野元春という新しい存在と彼の斬新な音楽をどんなふうに扱えばいいのか、わからなかったからじゃないか、と言うこともできるような気がします。
::::::::当時、音楽を紹介するメディアの側にも戸惑いがあったことは僕も記憶しています。
小坂 ええ。他人のせいにするつもりはないけど(笑)、どんなふうに紹介したらいいのか、というメディアの人たちの戸惑いみたいなものは僕らも感じていました。それまでのロックのイメージからは逸脱しているけど、だからといって既成のニュー・ミュージックの範疇に入るようなものでもない、ということですね。花開くまでには時間がかかりましたが、まったく新しいものが登場したとき、というのはそういうものじゃないか、とも思います。
|
|
|



